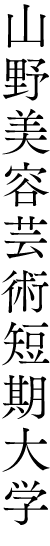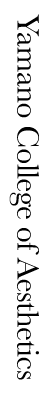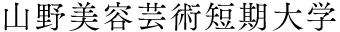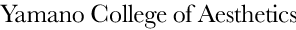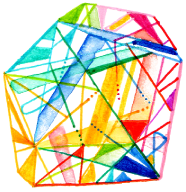
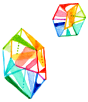
教職員研修会実施状況
過去の教職員研修会実施状況
| 回数 | 日付 | 発表内容 | 講演者・発表者 |
|---|---|---|---|
| 21 | 平成29年 3月23日 |
平成29年度からの新しい教職員の紹介 | 木村康一・副学長 |
| 短大 ディプロマポリシー 新しい教育方法(レゴ、アイコンetc) 新しい入試システムについて(高大接続) 各専攻の新しいプログラム |
木村康一・副学長 | ||
新しい教育法ワークショップについて
|
木村康一・副学長 大野淑子・教授、平田昌義・准教授 |
||
| シデスコについて | 吉田真希・准教授 | ||
| スカイキャンパス(タブレット)の運用 | 倉橋美香子 | ||
| 心の問題ワークショップについて | 栗本佳典・教授 | ||
| 非常勤講師会 | |||
| 20 | 平成28年 8月12日 |
研究成果発表
|
秋田留美・教授 八槇達也・助教 秋田留美・教授 富田知子・教授 文元麻理香・講師 鈴木ひろ子・教授 鈴木ひろ子・教授 |
| スカイキャンパス検討状況の報告 | 馬場祐造・事務局長 | ||
| 自己点検・評価報告書の共有 | 木村康一・副学長 | ||
| アクティブ・ラーニング研修 | 帝京大学 准教授 教育方法研究支援室 宮原俊之 |
||
| 19 | 平成28年 3月25日 |
本学の方向性について(中長期計画) | 木村康一・副学長 |
| 留学生対応について | 実森雄介・教務課主任 | ||
| カリキュラム・ツリーとカリキュラム・マップについて | ティミー西村・教授 | ||
| 入試システムについて(高大接続) | 戸谷宰之・広報課長 | ||
| 模擬授業 久保村千明 准教授 今井博啓 准教授 |
全教職員参加 | ||
| 18 | 平成27年 8月12日 |
研究成果発表
|
秋田留美・教授 八槇達也・助教 吉田真希・准教授 五十嵐靖博・教授、鈴木ひろ子・教授、三谷玲子・講師 トニー コール・講師 文元真理香・講師、田嶋順子・兼任講師、富田知子・教授、大西典子・准教授、及川麻衣子・准教授 栗本佳典・教授、河野誠二・兼任講師、酒井朋恵・講師、菊池信二・兼任講師、吉川奈菜子、富田知子・教授 町田喜代美・講師、八槇達也・助教、武藤祐子、西村伸大、富田知子・教授 鈴木ひろ子・教授、木村康一・教授、加藤友美・准教授、ジョン パーカー・准教授 |
| 今後の本学の動きについて(中長期計画) | 木村康一・副学長 | ||
| 第三者評価の取り組みについて | 木村康一・副学長 | ||
| 模擬授業 加藤友美 准教授 上妻直博 講師 |
全教職員参加 | ||
| 体験授業(ブレイド体験) | 全教職員参加 | ||
| 17 | 平成27年 3月26日 |
第三者評価を受けるにあたって | 木村康一・副学長 |
| キャリア指導(履歴書指導)について | 鈴木ひろ子・教授 斉藤光洋・事務局次長 |
||
| 各専攻の学習成果カルテについて | ティミー西村・教授 | ||
| 模擬授業 吉田真希 准教授 |
全教職員参加 | ||
| 16 | 平成26年 8月28日 |
第三者評価について | 木村康一・副学長 |
| 災害時の対応について 災害時の誘導法、ケガの応急処置、AEDの使用法 |
東京消防庁 | ||
| 模擬授業 栗本佳典 教授 ジョン・パーカー 准教授 |
全教職員参加 | ||
| メンタル学生対応について | 岡田奈緒子・保健管理室長 他カウンセラー、看護師 |
||
| 15 | 平成26年 3月27日 |
SNSについて(基本知識/問題) | 木村康一・副学長、久保村千明・講師 |
| 美容福祉の今後について | 田嶋順子・教授、大西典子・准教授 | ||
| 模擬授業 加藤宏美 講師 ティミー西村 教授 |
全教職員参加 | ||
| 14 | 平成25年 8月28日 |
本学学生におけるメンタルヘルスの現状と課題について 保健管理室の利用状況 メンタル不調者の現状報告 学生のSOSサインを見逃さない メンタル不調者との上手なコミュニケーションの取り方 体調不良者が出た時の対応 症例から見た精神疾患の特徴と傾向(病気への理解と学生との関わり方を考える) 保健管理室の役割と課題 教職員からの質疑応答 教職員のメンタルヘルスの重要性(ストレスチェック) |
岡田奈緒子・保健管理室長 |
| 模擬授業 木村康一 副学長 トニー・コール 講師 三谷玲子 講師 平田昌義 准教授 |
全教職員参加 | ||
| 13 | 平成24年 8月27日・28日 |
第1日目 ハラスメントに関するケース紹介 |
木村康一・副学長 |
| 留学生サポート体制 | 中野陽介・広報課員 | ||
| カリキュラム発表 | 松下能万・学生教務委員長 | ||
| ロジカルシンキング グループディスカッション | 全教職員参加 | ||
| フリーディスカッション | 全教職員参加 | ||
| 第2日目 研究発表 Pivot Pointマインドフルティーチング教育システム研究 美容コンテスト入賞に向けた技術力向上のための研究 英語教育センターの取り組み -現状と今後への展望 重症心身障害児施設における美容ケアの実際 新しい心理学・カウンセリング教育を目指して 美容作業を向上させる香りの探索 スキャルプケアの研究について |
全教職員参加 平田昌義・講師 他 河野誠二・教授 ジョン パーカー・准教授 他 荒井典子・講師 鈴木ひろ子・准教授 他 武藤祐子・講師 他 下家由起子・講師 他 |
||
| 学生のメンタルに関する事例報告・質問会 | 新永和子・看護師 | ||
| グループディスカッションセッション | 全教職員参加 | ||
| 内容プレゼンテーション | 全教職員参加 | ||
| 12 | 平成23年 9月7日 |
キャリア教育実践の現場と未来 | 大野淑子・准教授 松下能万・准教授 |
| エステティック業界における資格制度について 総合エステティック専攻の取り組み |
吉田真希・講師 | ||
| 11 | 平成23年 6月25日 |
学校法人山野学苑について | 学苑全教職員参加 |
| 初代・山野愛子について | 学苑全教職員参加 | ||
| 美道とは | 学苑全教職員参加 | ||
| 美道五大原則とは | 学苑全教職員参加 | ||
| ビューティ・マナー 髪・顔・装い・健康美・精神美 |
学苑全教職員参加 | ||
| 山野愛子ジェーンからのメッセージ | |||
| 10 | 平成22年 10月5日 |
第2回 森吉弘(森ゼミ)セミナー | 森吉弘・森ゼミ主宰 |
| 9 | 平成22年 8月12日 |
学長講話 | 山野正義・学長 |
| 新学科開設に向けて | 木村康一・副学長 | ||
| シラバス作成等について | 鎌田正純・教務委員長 | ||
| 今後のキャリア支援について | 大野淑子・キャリア支援センター副センター長 | ||
| 森吉弘(森ゼミ)セミナー | 森吉弘・森ゼミ主宰 | ||
| 8 | 平成21年 8月10日 |
山野美容芸術短期大学の現状と将来 | 山野正義・学長 |
| マナーに関する講義 | 原田公子・山野美容専門学校教員 | ||
| 大学生によく見られる代表的な精神疾患の治療と対処法について | 岡田奈緒子・准教授 | ||
| グループ討議 学生の学習意欲向上や受講態度改善について、これまでの教職員研修会等の提案により実行された対策の検証と新たな提案、および、今後取り組むべき課題に対する提案について 討議テーマ
|
全教職員参加 | ||
| 講話 | 山野愛子ジェーン・副学長 | ||
| 7 | 平成20年 8月8日 |
学生の満足度の向上について | 山野正義・学長 |
| 「山野」の教職員のあり方と学生指導 | 山野愛子ジェーン・副学長 | ||
| Mission Statement | 中川巧スタン・総括 | ||
| 少年院と少年院での教育 | 中野レイ子・駿府学園長 | ||
| 平成18、19年度卒業時アンケートにみる学生像 | 鎌田正純・准教授 | ||
| 福祉実習の体験 | 全教職員参加 | ||
| グループ討議 「学生の満足度向上のために」 |
全教職員参加 | ||
| 6 | 平成19年 8月1日 |
学生募集に繋がる教育方法の改善等について | 山野正義・学長 |
| 学生指導と教育のあり方について | 山野愛子ジェーン・副学長 | ||
| 「改善」について | 中川巧スタン・総括 | ||
| 教育の充実について -退学・休学生の純減を目指して | 生山 匡・教務委員長 | ||
グループ討議
|
全教職員参加 | ||
| 美容実習(ヘアー)の体験 | 全教職員参加 | ||
| 5 | 平成18年 8月7日 |
美容教育七つの原則・三つの核 | 山野正義・学長 |
| 平成19年度学生募集における経過と分析結果 | 生山 匡・教務担当学長補佐 | ||
| 短大の魅力と創造すべき魅力に関する本学学生と教職員の認識(学生募集に役立たせるためと短大教育の向上のために)(昨年度FD結果の活用) | 近藤陽一・美容芸術学科長兼美容保健学科長 | ||
| 介護福祉士制度の見直し案について | 竹田幸司・講師 | ||
| 習熟度別クラス編成の事例について | 河野誠二・教授 | ||
| 英会話教育の事例 | 大谷加代子・助教授 | ||
| 4 | 平成17年 8月6日 |
新たな挑戦のスタートに | 山野正義・学長 |
| コミュニケーション・マナー | 山野愛子ジェーン・副学長・専攻科長 | ||
| 個人情報保護法の考え方について | 村田明彦・弁護士 | ||
| 山野美容芸術短期大学の美容師養成施設としての位置と魅力 | 木村康一・学生担当学長補佐 中原直人・講師 |
||
グループ討議
|
全教職員参加 | ||
| 3 | 平成16年 7月29日 |
教員研修の目的と美容師にとっての「マナー」 | 山野正義・学長 |
| 「第1印象をよくすること」が大事です | 山野愛子ジェーン・副学長 | ||
| 喫煙(禁煙)マナー教育の経過、現状、将来 | 木村康一・学生委員長 | ||
| マナーの全貌 | 生山 匡・教務担当学長補佐 | ||
グループ討議
|
全教員、主任以上職員参加 | ||
| 2 | 平成15年 7月27日 |
「生きるほどに美しく」と山野学苑の使命 | 山野正義・学長 |
| ジャーナリズムとファッションの現場 | 大島幸夫 毎日新聞元特別編集委員 |
||
| 美容教育における美術(造形芸術)教育の意味と役割 | 伊藤繁夫・教授 | ||
| デッサン、絵画、色彩と造形について | 栗本佳典・助教授 | ||
| 彫刻の基礎教育について | 大須賀万里子・教授 | ||
| 美術理論系の授業について | 澤村英子・講師 | ||
| 短大の英会話授業-サロン英語の特殊性 | 大谷加代子・助教授 | ||
| 福祉に生かす美容教育・・・美容福祉学科の教育・研究と実践 | 渡辺聰子・教授 | ||
| 美容師国家試験・筆記試験対策への対応 | 生山 匡・美容師試験対策委員会 筆記試験部会長 |
||
| 「技能成績管理評価システム」の試行報告 | 河野誠二・教授 | ||
| 1 | 平成14年 7月26日、27日 |
工程表教育ではなく創造的な教育を | 山野正義・学長 |
| 18歳人口の今日、その意識と行動 | 岩間夏樹・若者文科研究所 | ||
| 今、セクハラ問題の課題は、対応は | 石垣忠・社会保険労務士 | ||
| さらなる主題設定を授業改善から我が短大の社会的認知の上昇へ | 森 清・学長室長 |